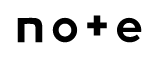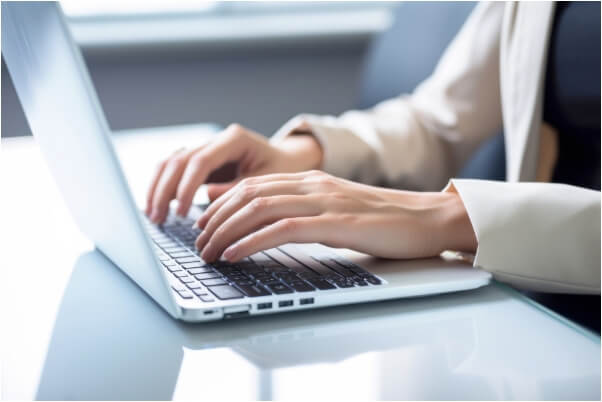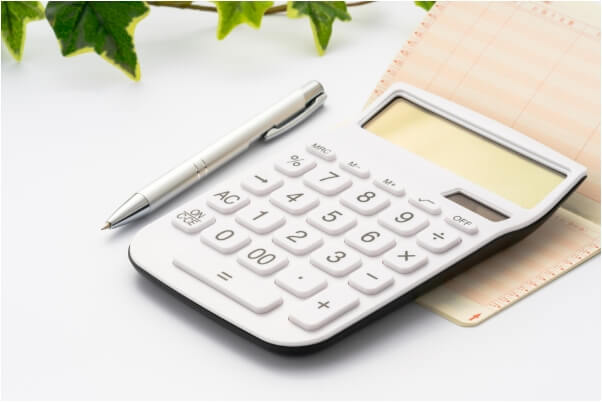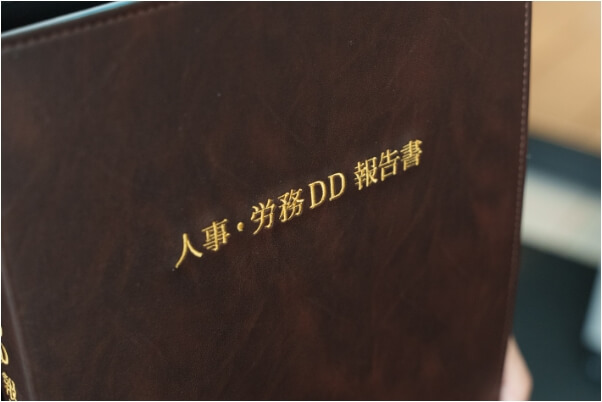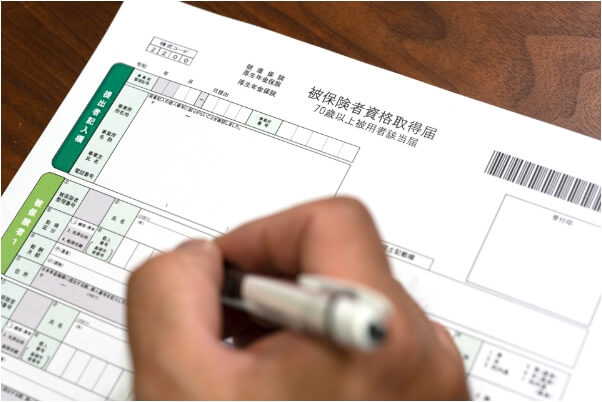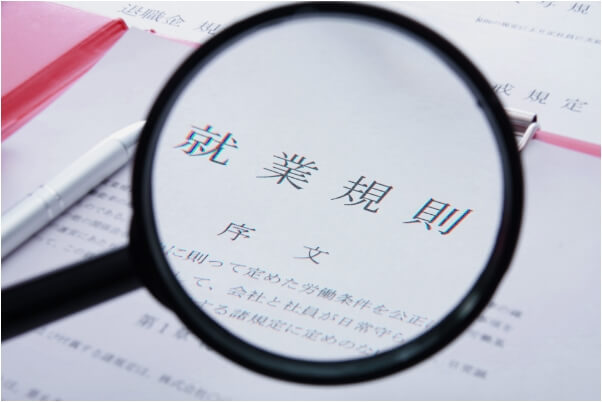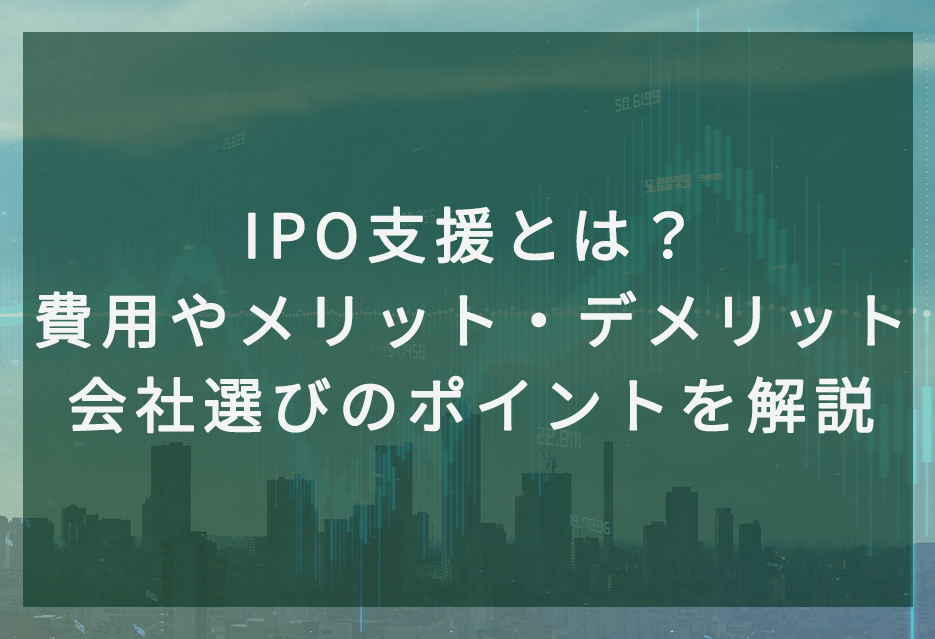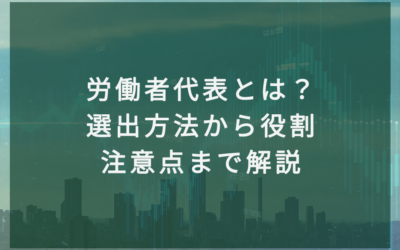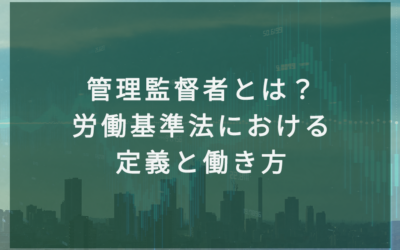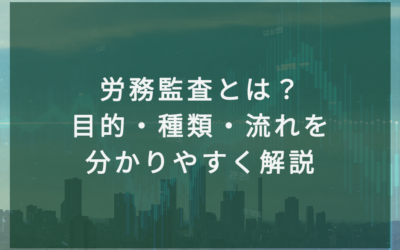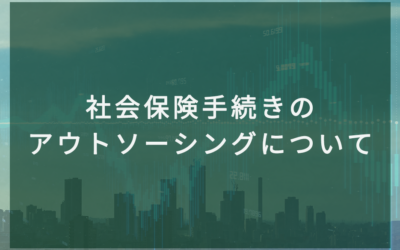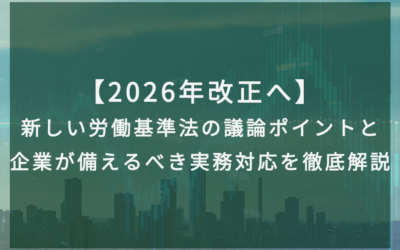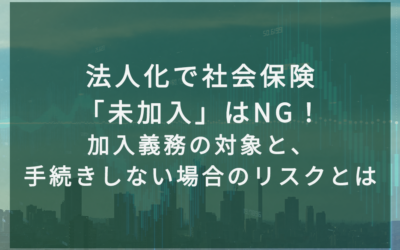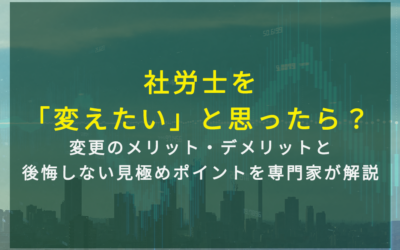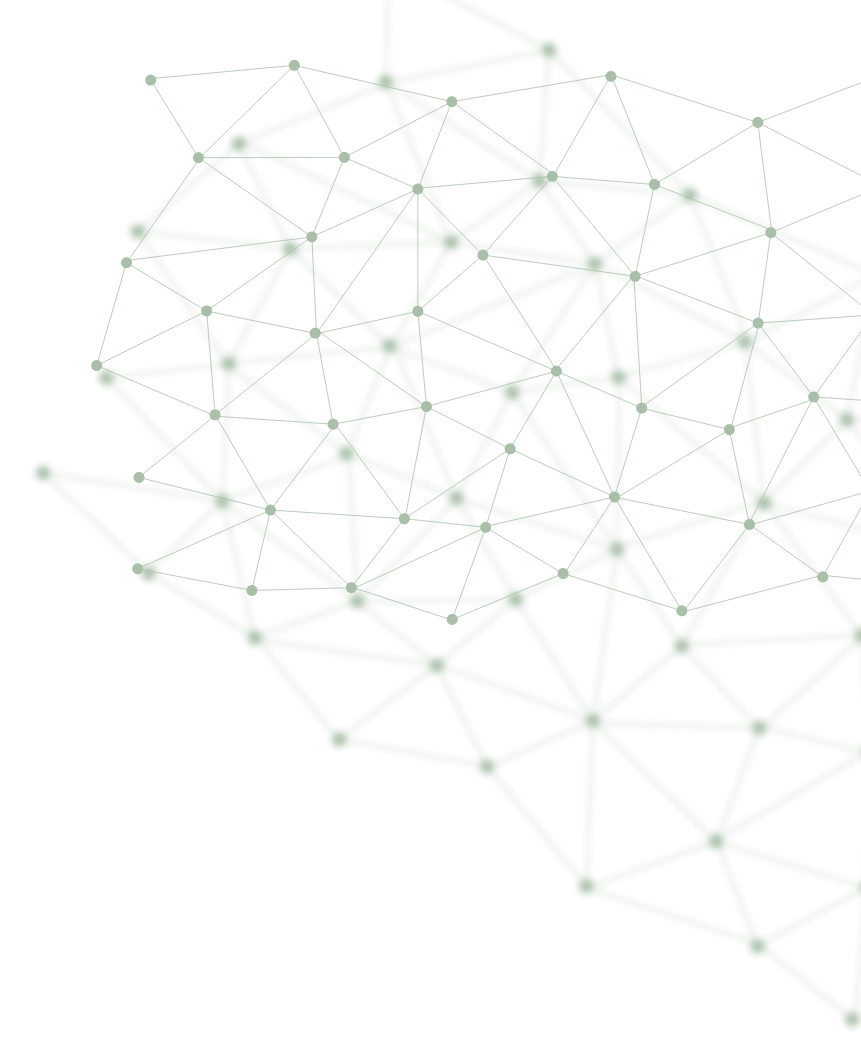近年、スタートアップや中堅企業を中心に、新規株式公開(IPO)を目指す企業が増加しています。
しかし、IPOは単に株式を公開するだけではなく、上場審査を通過するための厳格な準備と社内体制の整備が求められる、極めて高度で専門的なプロジェクトです。
そのため、企業単独での上場準備には限界があり、外部の「IPO支援」を受けることが極めて重要となります。
本記事では、IPO支援の基本的な仕組みや種類、メリット・デメリット、費用相場、さらに信頼できる支援会社を選ぶためのポイントについて、網羅的に解説します。
IPO支援とは?
IPO支援とは、企業が株式上場を実現するために必要な準備や手続きを、外部の専門家がサポートするサービスです。
上場審査における内部管理体制や財務の透明性、ガバナンスの強化といった分野において、専門知識を持つ支援者が伴走し、スムーズなIPOの実現を支援します。
IPO支援が重要になる理由
IPOを目指す企業にとって、上場基準を満たすためには、財務報告の適正化、コンプライアンス体制の構築、事業計画の明確化など、非常に多岐にわたる要素が求められます。
さらに、上場審査を通過するには、証券取引所や主幹事証券会社との綿密なコミュニケーションも必要です。
こうした準備を自社のリソースだけで行うのは困難であり、ミスがあれば上場審査での減点や、最悪の場合には上場延期というリスクもあります。
そのため、専門知識と経験を有する外部支援の重要性が高まっているのです。
IPO支援の種類と支援内容
IPO支援には複数の形態が存在し、支援者の立場や専門性によって提供されるサービスの内容が異なります。
主な支援者は以下の通りです。
①会計士系コンサルタント
公認会計士出身者が中心となって行う支援です。
財務諸表の適正化や内部統制報告制度(J-SOX)への対応、開示資料の整備など、主に財務・会計分野での支援が得意です。
経理部門の体制強化や決算早期化の支援にも実績があります。
主な支援内容
| 支援領域 | 具体的な業務内容(SEO強化キーワード) |
| 財務・会計体制の整備 | 経理部門の組織化および体制強化、決算早期化の実現支援、上場基準に準拠した会計処理への移行および運用アドバイス。 |
| 内部統制の構築 | 内部統制報告制度(J-SOX)対応の支援、販売・購買・給与など主要業務プロセスに関する規程・マニュアルの整備、IT統制の構築および運用支援。 |
| 開示資料の整備 | 有価証券報告書や事業計画書など、上場申請に必要な開示資料の作成支援、適時開示体制の構築。 |
| 監査法人対応 | 監査法人との連携、会計監査対応のサポート、指摘事項への改善策立案と実行支援。 |
特徴と強み
- 監査目線での指導: 監査法人出身者が多いため、監査法人がチェックするポイントを熟知しており、手戻りが少ない指導が可能です。
- 専門性と信頼性: 財務諸表の信頼性を高め、投資家からの信頼を得るための基盤構築に最も貢献します。
②証券会社系コンサルタント
主幹事証券会社のOBなどが在籍するコンサルティング会社です。
証券取引所との調整、株式公開スケジュールの策定、資本政策の立案など、証券業界との連携を強みとしています。
審査目線でのアドバイスを受けられる点が特徴です。
主な支援内容
| 支援領域 | 具体的な業務内容 |
| 株式公開プロセス | 全体スケジュール(マスタープラン)の策定および進捗管理、主幹事証券会社・監査法人の選定支援、証券取引所への上場申請書類(Ⅰの部・Ⅱの部など)の作成支援。 |
| 資本政策・ファイナンス | 資金調達計画の立案、株式発行価格・公開株数の決定支援、ストックオプションや信託型報酬などのインセンティブ制度設計。 |
| 審査・市場対応 | 証券取引所や主幹事証券会社からの審査質問への対応アドバイス、IR(投資家向け広報)体制の構築支援、上場後の株価対策に関する助言。 |
| 事業計画 | 成長可能性を示す事業計画の策定支援(特にグロース市場向け)、事業内容と資本政策の整合性検証。 |
特徴と強み
- 市場との連携: 証券業界との強固なネットワークを持ち、審査目線でのアドバイスを提供。上場実現までの最短ルートを設計する能力に優れています。
- 資金調達の最適化: 資本政策の専門知識に基づき、会社の価値最大化と創業者の支配権維持のバランスを取りながら、最適なファイナンス戦略を立案します。
③士業
弁護士、社会保険労務士、税理士などの士業もIPO支援を行います。
法務・労務・税務の分野でのコンプライアンス対応やリスクマネジメントの整備を支援します。
企業のガバナンス体制の構築には不可欠な存在です。
主な支援内容
| 士業の種類 | 支援領域 | 具体的な業務内容 |
| 弁護士 | 法務・ガバナンス | 株主総会・取締役会運営体制の整備、各種契約書のリーガルチェックおよび標準化、訴訟リスクの調査と対応、知的財産管理体制の構築支援。 |
| 社会保険労務士 | 労務・人事 | 労働時間管理の適正化、未払い残業代リスクの調査と是正、就業規則や人事評価制度の整備、社会保険・労働保険の適正加入状況の確認および改善提案。 |
| 税理士 | 税務 | 税務リスクの調査と是正、事業承継や組織再編に関する税務アドバイス、連結納税への移行支援、税効果会計の適用支援。 |
特徴と強み
- リスクマネジメント: 企業の潜在的な法的・労務的リスクを早期に発見し、上場前にクリーンな状態に是正する専門性を持っています。
- ガバナンス体制の基盤: 法制度に基づいた機関設計や内部規程の整備を通じて、企業のガバナンス(統治体制)の基盤を確立します。
④その他専門家
企業経験者やIPO経験のあるCFO(最高財務責任者)人材など、個人ベースで支援を提供する専門家も存在します。
特定のフェーズ(たとえばCFO不在の企業への人材派遣)でのスポット支援など、柔軟な対応が可能です。
主な支援内容
| 支援領域 | 具体的な業務内容 |
| CFO機能の補完 | CFO代行(ハンズオン)としての参画、経営層と現場をつなぐ実務的なリーダーシップ、経営会議や取締役会への参加。 |
| 人材派遣・育成 | IPO準備に必要な経理・財務・IR担当者の派遣、社内キーパーソンへのOJT(オンザジョブトレーニング)を通じた人材育成。 |
| 特定の課題解決 | 月次決算の早期化、予実管理の仕組みづくり、特定のシステム導入におけるプロジェクトマネジメントなど、スポット的な支援。 |
| 成長戦略 | 事業計画と予実管理の連携、上場後の成長を支える組織設計や企業文化の醸成に関するアドバイス。 |
特徴と強み
- 柔軟性と即戦力: 必要なフェーズやスキルに応じてピンポイントで契約できるため、柔軟な費用設定と即座の戦力化が可能です。
- 経営者目線: 実際に上場を経験したCFOなどが多いため、単なる手続き論ではなく、経営者や現場の立場に立った実務的なアドバイスと実行支援を提供できます。
- 特定のニッチな知見: 特定の業種(例:ITベンチャー、バイオテックなど)や、特定の市場(例:グロース市場)での上場に特化した深い知見を持つケースが多くあります。
IPO支援を受けるメリット・デメリット
IPO支援を受けるメリット・デメリットはどのようなものがあるのでしょうか。
それぞれ解説します。
メリット
メリットは下記のような点です。
それぞれ詳しく解説します。
①上場準備のスピードと正確性が向上する
IPOには数百項目に及ぶ準備作業があり、それぞれに専門的な知識と判断が必要です。
IPO支援を受けることで、各タスクを「どのタイミングで」「どう進めるべきか」のロードマップが明確になり、余計な試行錯誤や手戻りが避けられます。
特に初めてIPOを目指す企業では、「何から着手すべきか」が分からず、時間を浪費しがちです。
支援者の指導により、最短ルートで効率的に進行できる点は非常に大きなメリットです。
②制度対応やガバナンス強化が確実に行える
IPOでは、金融商品取引法、会社法、上場審査基準など複雑な法制度に対応する必要があります。
内部統制報告制度(J-SOX)や、取締役会の機能強化、監査体制の整備なども求められます。
支援者はこうした制度やガバナンス整備の経験が豊富で、監査法人や証券会社がチェックするポイントを熟知しています。
そのため、審査基準に確実に適合する体制を、着実に構築することができます。
③社内人材の育成と意識改革につながる
IPO支援の過程では、財務部門、人事部門、総務部門などが連携しながら「上場企業水準の業務」を学んでいくことになります。
外部支援者の指導により、業務品質やコンプライアンス意識が向上し、上場後の会社運営にも役立つ“人材力”が身につきます。
特に成長企業では、制度設計や業務分掌が曖昧なケースも多く、IPO支援を通じて「企業としての基盤強化」が進むことは長期的にもプラスとなります。
④金融機関・投資家からの信頼性が高まる
信頼ある支援会社の関与は、外部ステークホルダーに対する安心材料にもなります。
主幹事証券会社や監査法人、ベンチャーキャピタルにとっても、適切な外部支援があることで、企業の上場意欲や準備の真剣さが伝わりやすくなります。
場合によっては支援会社が主幹事証券会社やCFO人材などを紹介するケースもあり、人的ネットワークの面でも大きな利点があります。
デメリット
デメリットは下記のような点です。
それぞれ詳しく解説します。
①多額の支援コストが発生する
IPO支援には、数年にわたって外部専門家を活用することになるため、費用は年間で数百万円〜数千万円に及ぶケースがあります。
支援会社の規模や関与の深さによって費用は異なりますが、経営者としては事業投資とのバランスを見極めながら判断する必要があります。
②社内リソースに大きな負担がかかる
「支援がある=丸投げできる」わけではありません。
実際には、支援者の指示や助言に基づいて、社内の各部門がドキュメント整備や業務改善を行う必要があり、既存業務に加えて大きな負荷がかかります。
特に中小企業やスタートアップでは、担当者が兼務状態であることが多く、過労やモチベーション低下につながるリスクもあります。
③支援者とのミスマッチリスクがある
支援者との相性や期待値のズレがあると、効果的な支援が受けられません。
たとえば、特定業界に詳しくない支援者、IPO経験が少ない支援者に依頼してしまうと、実務との乖離が発生し、逆に混乱を招くこともあります。
また、支援スタイルが上から目線・一方的指導型であったり、現場との信頼関係を構築できない支援者に当たってしまうと、社内に不満や反発が生じるケースもあります。
④IPOありきの進め方になるリスク
外部支援者の一部には、「とにかくIPOを目指す」スタンスで企業に対し急進的な施策を推奨する場合もあります。
しかし、本来IPOは「手段」であり、企業の成長戦略の一環にすぎません。
無理にIPO時期を早めると、体制が未整備のまま上場するリスクがあり、上場後に経営不祥事や業績不振などに陥る恐れもあります。
支援者とともに、あくまで自社の成長に即したペースで進めることが求められます。
このように、IPO支援には多くのメリットがある一方で、導入に際しては費用・人材・相性といった慎重な検討が不可欠です。
支援者との連携がうまくいけば、単なる「上場支援」にとどまらず、企業の体質強化と飛躍的な成長にもつながる貴重な投資となるでしょう。
IPO支援の費用相場
IPO支援にかかる費用は、支援内容の範囲や期間、支援者の種類によって異なります。
以下は一般的な相場です。
| 会計士系コンサルタント:月額50〜150万円程度
証券会社系コンサルタント:月額100〜200万円程度 弁護士・社労士などの士業:スポット契約や顧問契約で月額10〜30万円 その他専門家:業務委託形式で月額20〜100万円 |
IPO支援会社の選び方
IPO支援は長期にわたる伴走型の支援となるため、信頼できる支援会社を選定することが成功の鍵です。
以下の観点から慎重に検討しましょう。
①IPOの実績が豊富にあるか
支援会社の過去のIPO支援実績は非常に重要です。
どのような規模・業種の企業を支援してきたか、上場までの成功率などを確認しましょう。
②専門性があるかどうか
会計、法務、労務、内部統制など、それぞれの分野での専門知識が求められます。
自社の課題に応じた専門性を持つ支援者を選ぶことが重要です。
③費用体系が明確かどうか
支援内容と費用のバランスが取れているかを確認し、不明瞭な追加費用が発生しないか、契約前にしっかりと説明を受けましょう。
④上場後のサポートもしてくれるかどうか
上場後の開示対応や内部統制の継続的な運用など、上場後も支援を継続してくれるかどうかも重要なポイントです。
まとめ
IPO支援は、上場を目指す企業にとって非常に重要なパートナーとなる存在です。
上場審査を乗り越え、株式市場で信頼を得るためには、財務・法務・労務・ガバナンスといった幅広い分野での支援が不可欠です。
適切な支援者を選び、計画的かつ戦略的に上場準備を進めることで、企業はよりスムーズにIPOを達成し、さらなる成長へとつなげることができるでしょう。
費用や体制面の準備も含め、早期からの準備が成功へのカギとなります。
人事労務に関するお悩みサポートします!
- 社会保険の手続き、いつも手間取る…
- 勤怠管理にムダが多い気がする
- 助成金って、うちも使える?
- 労務管理が属人化してて心配
一般的な労務業務だけでなく、
IPO支援労務コンサルティング・M&A・労務・人事DD等の
幅広い業務に全国で対応可能です。
365日/24時間受付

監修者海蔵 親一
社会保険労務士・行政書士・社会福祉士
「経営者と同じ目線で考え、行動すること」をモットーに、現場に即した実効性のある支援を行っている。