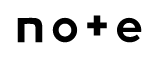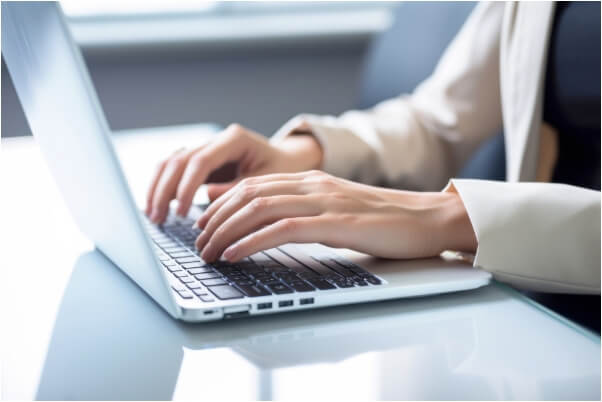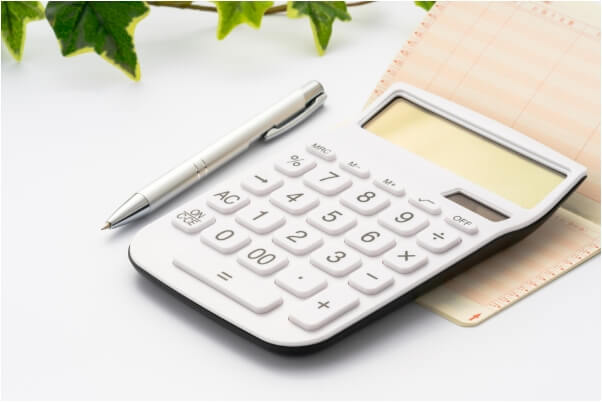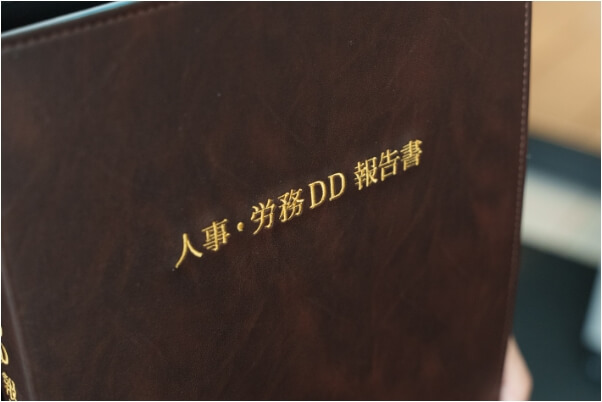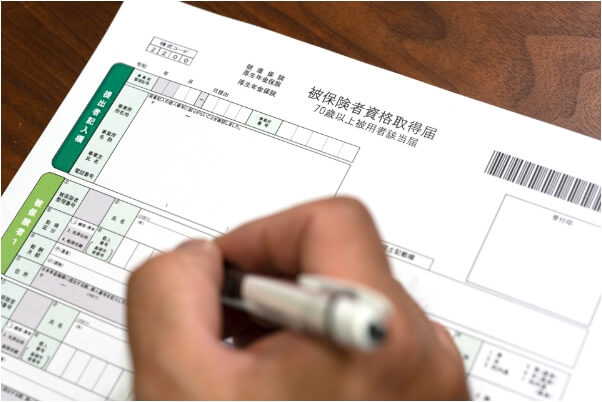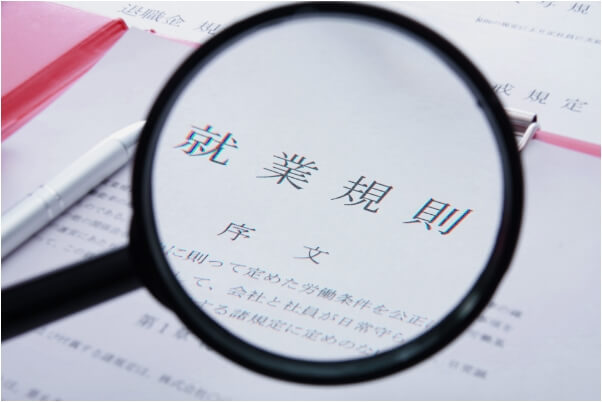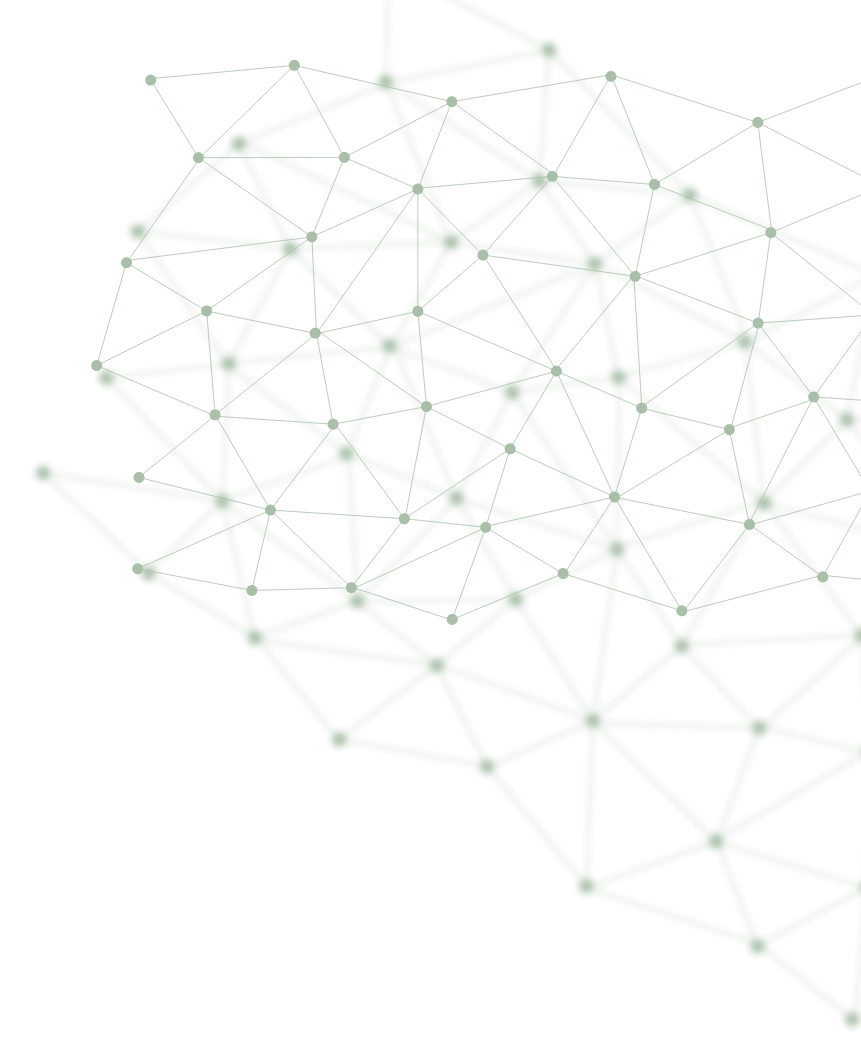【1】2025年度の法改正等まとめ
【雇用保険法】
■施行日:2025年4月1日
01 高年齢雇用継続給付の見直し
※2025年4月以降に60歳に達した労働者が対象。
高年齢雇用継続給付金の支給率が最大15%⇒10%へ改定
高年齢雇用継続給付金は段階的に縮小され、将来的に廃止が決定しています(時期未定)。給付金の支給率が減額されることに伴い、賃金制度の見直しが必要になります。
02 ⾃⼰都合離職者の給付制限の⾒直し
※自己都合退職の給付制限 2ヶ月→1ヶ月へ短縮
※離職前後(離職前は1年以内)に教育訓練を受講した場合は、自己都合離職における失業給付(基本手当)の給付制限なし
03 育児休業給付金 2025年4月1日より受給延長手続きの厳格化へ
※追加確認書類 ①本人記載の申告書 ②保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し
・ 利用を申し込んだ保育所等が、合理的な理由なく、自宅又は勤務先からの移動に相 当の時間を要する施設のみとなっていないこと
・ 市区町村に対する保育利用の申込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示を行っていないこと
04 育児休業給付の給付率引上げ
※被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付し、育児休業給付とあわせて給付率80%(手取り100%)へと引き上げ
05 育児時短就業給付の創設
※2歳未満の子を養育する時短勤務者に対し、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を給付
ただし、時短後の賃金と給付額の合計が時短前の賃金を超えないよう調整する予定
■施行日:2028年10月1日
07 雇用保険の適用拡大
※雇用保険の被保険者の要件のうち、1週間の所定労働時間 20時間以上→10時間以上
【育児・介護休業法】
■施行日:2025年4月1日
08 小学校就学前の子を養育する労働者「所定外労働の制限(残業免除)」の対象を拡⼤
※法改正前は3歳未満の子
08 ⼦の看護休暇の⾒直し
※法改正により、小学校就学の始期に達するまで→小学校3年生修了まで、取得事由の拡大
08 育児のためのテレワーク導⼊の努⼒義務化
※3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう措置を講ずることが努力義務化
08 育児休業取得状況の公表義務の拡⼤と次世代育成⽀援対策の推進‧強化
※公表対象の企業拡大 従業員1,000人超→300人超
08 介護離職防⽌のための個別の周知・意向確認と雇⽤環境整備等の措置が義務化
※介護離職防止のため、以下の措置の義務化
・介護を申し出た労働者に対して、原則として面談・書面交付により、両立支援制度に関する個別の周知・意向確認を実施
・介護が必要になる前の早い段階で、両立支援制度に関する情報提供を実施すること(40歳の節目の年齢など)
・仕事・介護の両立支援制度が利用しやすい雇用環境を整備の措置
■施行日:2025年10月1日
08 ⼦どもの年齢に応じた柔軟な働き⽅実現のための措置等が義務化
※3歳以上小学校就学前の子を養育する労働者が、柔軟な働き方を活用しながらフルタイムでも働ける措置も選べるようにするための措置
08 仕事と育児の両⽴に関する個別の意向聴取‧配慮が義務化
※本人または配偶者が妊娠出産を申し出たとき、育休制度の周知と育休等取得意向を聴取することを義務化。意向の聴取後、就業条件を定める際、意向に配慮しなければならない。配慮すべき事項:始業・終業の時刻、就業の場所、業務量、制度等の利用期間など
【障害者雇用促進法】
■施行日:2025年4月1日
09 障害者法定雇用率の除外率の引き下げ
※特定の業種での除外率が、一律10%引き下げ
■施行日:2026年7月1日
09 障害者の法定雇⽤率の引き上げ
※常用労働者に占める障がい者の法定雇用率を2.5%→2.7%へ引き上げ
【労働安全衛生規則】
■施行日:2025年1月1日
10 労働安全衛生関係の一部の手続の電子申請が義務化
【厚生年金保険法施行規則】
■施行日:2025年1月1日
11 3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類の省略
【2】両立支援等助成金の拡充
令和6年12月17日に令和6年度の補正予算が成立したことに伴い、同日から施行されることになりました。
●育休中等業務代替支援コースの拡充内容
①育休取得者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大140万円/人支給!うち最大30万円先行支給
⇒ 就業規則整備等を社労士に委託した場合業務体制整備経費20万円に拡充
②短時間勤務者の業務を代替する労働者に手当を支給すると、最大128万円/人支給!うち最大23万円先行支給
⇒ 就業規則整備等を社労士に委託した場合業務体制整備経費20万円に拡充
③支給対象となる企業規模を全産業一律300人以下に拡大!
●出生時両立支援コースの拡充内容 ※中小企業のみ対象
①第1種の受給実績(男性育休取得の助成金申請)がなくても、第2種(男性育休取得率の上昇30ポイント以上)の申請可能!
②育休取得率「30%以上UP & 50%達成」で60万円支給!
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001356071.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/001356090.pdf
人的資本経営の考えでは、男性が育児に参加しやすい環境を整えることで、
ワークライフバランスを推進し、多様性と包括性を強化し、従業員の満足度と企業のブランドイメージも向上します。
育休取得率向上の取組に助成金の活用もご検討ください。
【3】スタートアップ企業の役員の労働者性 厚労省通達
厚生労働省は、スタートアップ企業で働く者に対する労働基準法の適用に関する解釈を通達しました。役員が労基法上の労働者に該当するかどうかを判断する際の基準を示すものです。取締役などの役員は一般的には労働者に該当しないと考えられるとする一方、取締役であっても就任の経緯や取締役としての業務執行の有無、業務への対価の性質・額などを総合考慮しつつ、会社との実質的な指揮監督関係や従属関係を踏まえて労基法上の労働者と判断した裁判例があることに留意すべきとし、管理監督者に該当するか否かについても、実態に沿って総合的に判断すると指摘しました。
通達
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T241022K0010.pdf