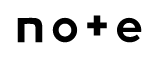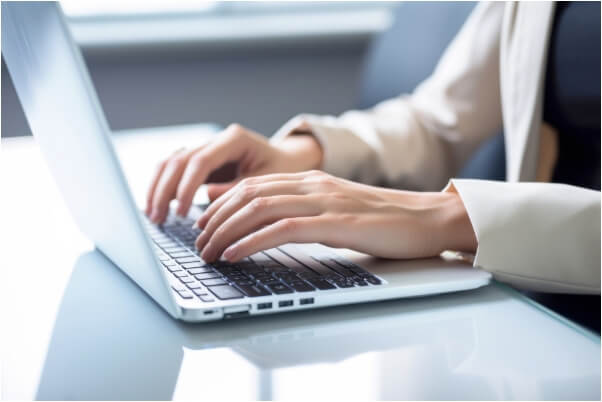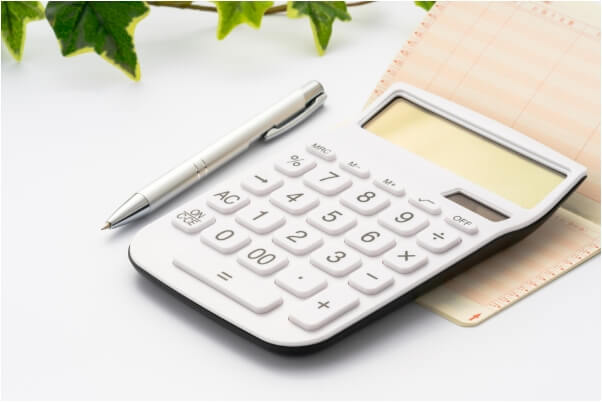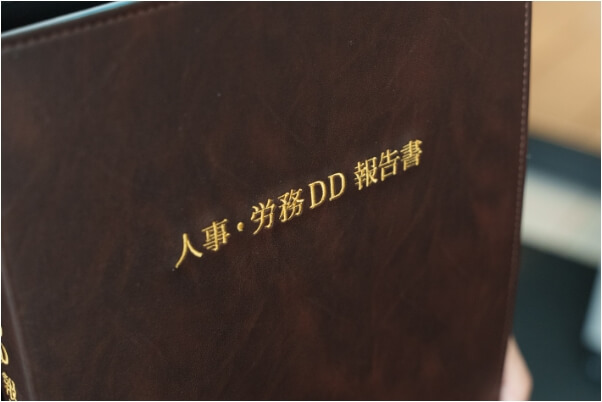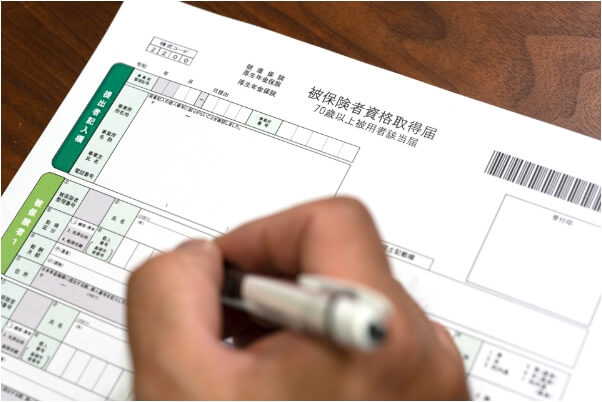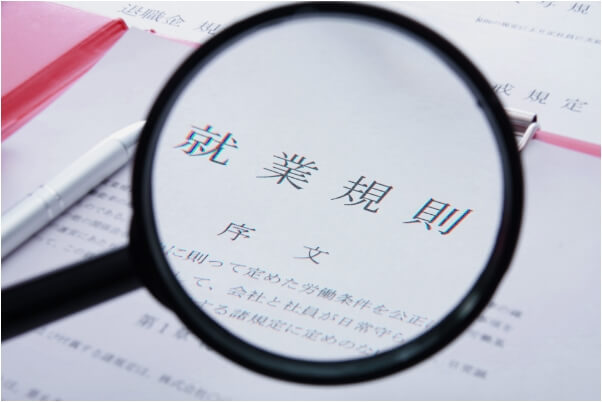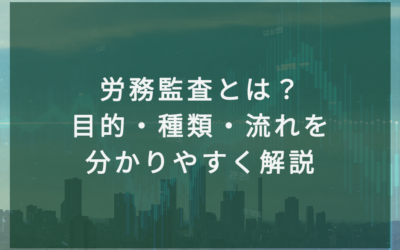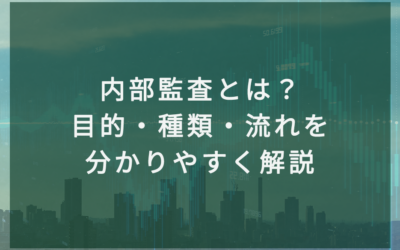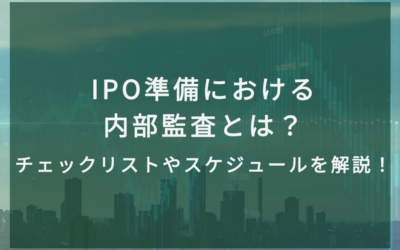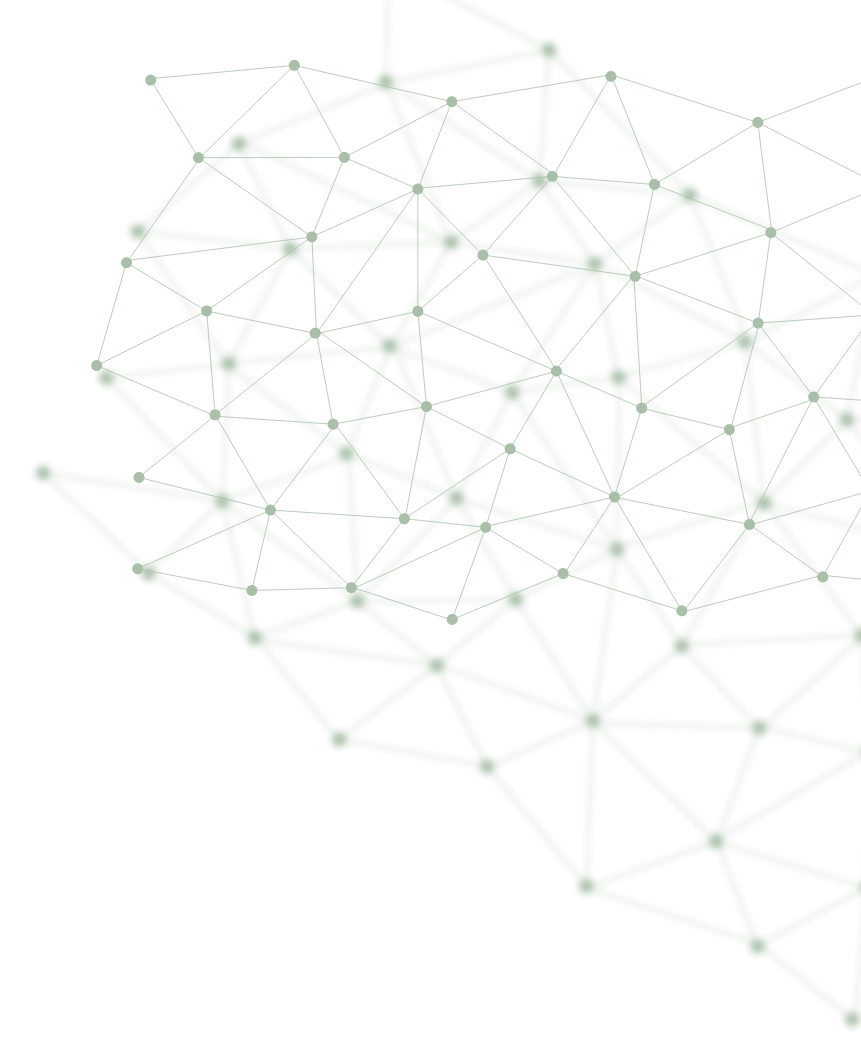企業において、労働時間や休日、残業の取り扱いを定める労使協定は欠かせない存在です。
特に「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」をはじめとした労使協定は、法令遵守と働き方改革の両立を図るうえで必須の手続きといえます。
その協定の締結において重要な役割を担うのが「労働者代表」です。
労働者代表は、労働組合が存在しない企業において、労働者の意思を集約し、使用者と交渉・合意を行う役割を果たします。
しかし、その選出方法や資格要件を誤ると、労使協定自体が無効と判断されるリスクがあり、残業代未払いの発生やIPO審査での重大な指摘につながる恐れがあります。
実際、労働基準監督署の調査では「会社が任意に指名した管理職が労働者代表とされていた」ため、36協定が無効とされ、数年分の未払い残業代を精算せざるを得なくなった事例も報告されています。
本稿では、労働者代表の定義から役割、選出方法、IPOを目指す企業が特に注意すべき点までを包括的に解説します。
労働者代表とは?
労働者代表とは、労働基準法に基づき、労使協定を締結する際に労働者の側を代表する者を指します。
労基法第36条は「使用者は、労働者の過半数で組織する労働組合、又は労働者の過半数を代表する者と書面による協定を締結しなければならない」と定めています。
この「労働者の過半数を代表する者」が、一般に「労働者代表」と呼ばれる存在です。
労使協定の対象は幅広く、次のようなものがあります。
- 時間外・休日労働に関する協定(36協定)
- 年次有給休暇の計画的付与に関する協定(労基法39条)
- 1年単位の変形労働時間制(労基法32条の4)
- 裁量労働制(労基法38条の3・4)
労働組合が存在する企業では、労働組合が労働者代表の役割を担います。
しかし労働組合の組織率は日本全体で約16%程度(厚労省データ)に過ぎず、多くの企業では労働者代表が選出されています。
労働者代表と労働組合の違い
労働組合は、労働組合法を根拠として結成され、団体交渉や労働争議などの強い権限を持つ組織です。
これに比べて労働者代表は、労使協定を結ぶ際にのみ選ばれる存在で、組織としての継続性や交渉権限はありません。
言い換えれば、労働組合は「労働条件に継続的に関与する組織体」であり、労働者代表は「協定のために一時的に選出される個人」です。
この区別を曖昧にすると、「代表を選んでいるのだから組合対策は不要だ」といった誤解につながりかねません。
労働者代表の主な役割
労働者代表の役割は、使用者と協議を行い、労使協定を締結することに尽きます。
しかし、この「協定を結ぶ」行為には大きな責任が伴います。
- 36協定への署名・押印
- 協定内容について従業員の立場から意見を述べる
- 協定後も従業員からの意見を吸い上げる窓口となる
例えば36協定では、月45時間・年360時間を超える残業は原則禁止されています。
これを超える労働を行わせるには「特別条項付き36協定」が必要ですが、この協定に署名するのも労働者代表です。
つまり、協定の内容が過重労働を助長するものであれば、その責任の一端を担う立場ともいえます。
労働者代表になるための要件
労働基準法において、労働者代表(過半数代表者)になるための主な要件は以下の5 点です。
これらの要件を満たさない者が選出された場合、締結した労使協定(36協定など)が無効になるリスクがあります。
管理監督者でない
労働者代表は「管理監督者」であってはなりません。
労基法上の管理監督者とは、経営者と一体的な立場にあり労働時間規制を受けない者を指します。
管理職であっても実態として裁量が乏しい場合は管理監督者に当たらないこともありますが、労働者代表には「一般従業員の立場に近い者」を選ぶのが原則です。
労働者の過半数の代表である
過半数とは「従業員数の半分を超える支持を得ている」ことを意味します。
たとえば従業員が100人なら、51人以上の支持が必要です。
少数の同意や一部の部署だけの合意では足りません。
使用者の意向に基づき選出された者ではない
使用者が「この人を代表にしてください」と指名することは認められません。
形式的にでも民主的な手続きを経て選ばれる必要があります。
形式違反は協定そのものの無効リスクを生みます。
労働者代表の選出方法
投票、挙手など、民主的な方法での選出が必要
選出方法は明確に「民主的」でなければなりません。
代表的な方法は投票ですが、規模が小さい事業所では挙手や全員の合意でも差し支えありません。
会社が一方的に指名してはいけない
「社長がA課長を労働者代表に任命した」という事例は無効とされます。あくまで従業員側が主体的に選出することが要件です。
正社員だけでなく、パートやアルバイトなども含めた全労働者が参加できること
選出には正社員だけでなく、パートやアルバイトを含む「全ての労働者」が参加しなければなりません。
非正規従業員を排除すれば、代表性を欠き無効リスクが高まります。
選出方法と結果を明確に記録しておくこと
投票結果の記録や掲示、議事録などを残しておくことが推奨されます。
IPO審査では「労働者代表の選出方法を示す証拠資料」の提示を求められることも多いため、記録は必須といえます。
IPOを目指す企業が労働者代表に関して注意すべきポイント
労働者代表の選出と協定運用は、IPO審査における「命綱」です。
形式的な整備だけでは不十分で、不適切な運用は上場審査の頓挫や、数千万円規模の残業代精算リスクに直結します。
ここでは、労務コンプライアンスの最重要課題である、労働者代表に関して企業が取るべき行動と注意点をご紹介します。
労使協定はIPO審査で必ずチェックされる
IPO審査では、労務コンプライアンスが極めて重視されます。
労使協定は形式だけ整っていればよいのではなく、選出過程の正当性まで確認されることがあります。
労働者代表の不適切な選出は、労使協定の無効につながるリスクがある
IPO準備中の企業で「協定に署名したのは管理職だった」ために指摘を受け、急遽再選出・協定再締結を求められた事例もあります。
協定が無効と判断された場合、残業代の未払いなどで労働基準監督署の指導対象となる可能性がある
協定無効=違法残業とみなされ、過去にさかのぼって残業代を支払わなければならなくなるケースは少なくありません。
上場審査中に数千万円単位の残業代精算が発生すれば、審査に大きな影響を及ぼします。
IPO支援に強い社労士に相談し、適切な労使協定の締結と運用を行うことが重要
IPO準備では、監査法人・証券会社・東証審査部からの質問に即答できる体制が必要です。
労働者代表の選出から協定運用まで一貫して整備するには、IPO実務を理解した社会保険労務士の支援が極めて有効です。
まとめ
労働者代表は、労使協定を適法に成立させるための不可欠な存在です。
その選出は民主的に行われ、管理監督者を除外し、全労働者の意思を反映する必要があります。
特にIPOを目指す企業にとって、形式的な協定では不十分であり、選出プロセスや証拠記録の整備まで含めた実務的な対応が求められます。
労務コンプライアンスはIPO審査の土台であり、軽視すれば上場自体が頓挫する危険もあります。
企業は「労働者代表」という仕組みを単なる形式ではなく、従業員との信頼関係を築く機会と捉え、適切な対応を行うことが重要です。
人事労務に関するお悩みサポートします!
- 社会保険の手続き、いつも手間取る…
- 勤怠管理にムダが多い気がする
- 助成金って、うちも使える?
- 労務管理が属人化してて心配
一般的な労務業務だけでなく、
IPO支援労務コンサルティング・M&A・労務・人事DD等の
幅広い業務に全国で対応可能です。
365日/24時間受付

監修者海蔵 親一
社会保険労務士・行政書士・社会福祉士
「経営者と同じ目線で考え、行動すること」をモットーに、現場に即した実効性のある支援を行っている。